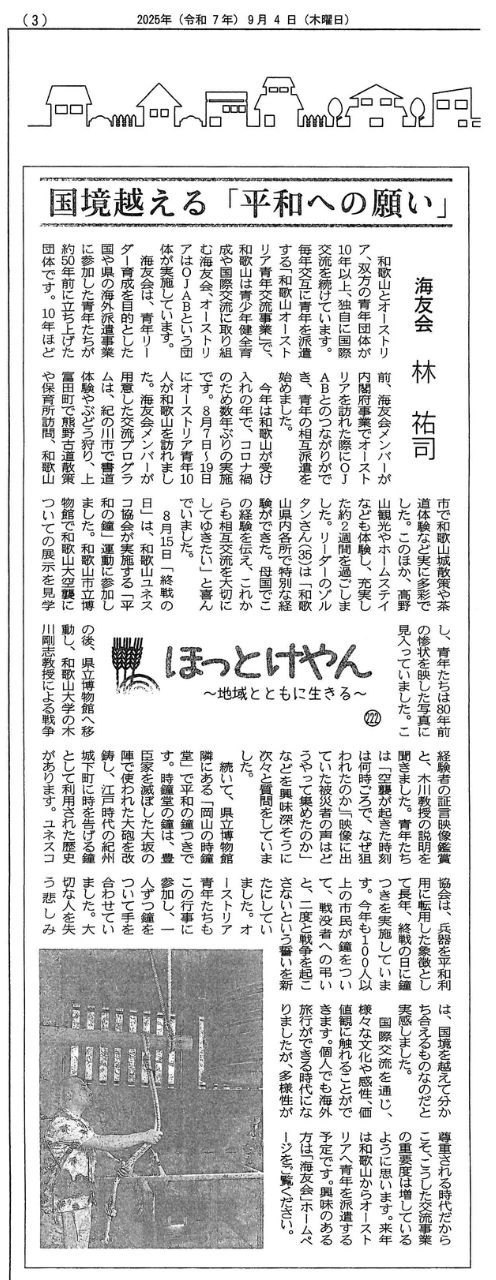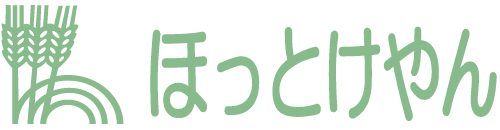ほっとけやん 第222話
わかやま新報2025年9月4日掲載
国境越える「平和への願い」
海友会 林 祐司
和歌山とオーストリア、双方の青年団体が10年以上、独自に国際交流を続けています。毎年交互に青年を派遣する「和歌山オーストリア青年交流事業」で、和歌山は青少年健全育成や国際交流に取り組む海友会、オーストリアはOJABという団体が実施しています。 海友会は、青年リーダー育成を目的とした国や県の海外派遣事業に参加した青年たちが約50年前に立ち上げた団体です。10年ほど前、海友会メンバーが内閣府事業でオーストリアを訪れた際にOJABとのつながりができ、青年の相互派遣を始めました。
今年は和歌山が受け入れの年で、コロナ禍のため数年ぶりの実施です。8月7日〜19日にオーストリア青年10人が和歌山を訪れました。海友会メンバーが用意した交流プログラムは、紀の川市で書道体験やぶどう狩り、上富田町で熊野古道散策や保育所訪問、和歌山市で和歌山城散策や茶道体験など実に多彩でした。このほか、高野山観光やホームステイなども体験し、充実した約2週間を過ごしました。リーダーのゾルタンさん(35)は「和歌山県内各所で特別な経験ができた。母国でこの経験を伝え、これからの相互交流を大切にしてゆきたい」と喜んでいました。
8月15日「終戦の日」は、和歌山ユネスコ協会が実施する「平和の鐘」運動に参加しました。和歌山市立博物館で和歌山大空襲についての展示を見学し、青年たちは80年前の惨状を映した写真に見入っていました。この後、県立博物館へ移動し、和歌山大学の木川剛志教授による戦争と平和に関する講義や経験者の証言映像鑑賞と、木川教授の説明を聞きました。青年たちは「空襲が起きた時刻は何時ごろで、なぜ狙われたのか」「映像に出ていた被災者の声はどうやって集めたのか」などを興味深そうに次々と質問をしていました。
続いて、県立博物館隣にある「岡山の時鐘堂」で平和の鐘つきです。時鐘堂の鐘は、豊臣家を滅ぼした大坂の陣で使われた大砲を改鋳し、江戸時代の紀州城下町に時を告げる鐘として利用された歴史があります。ユネスコ協会は、兵器を平和利用に転用した象徴として長年、終戦の日に鐘つきを実施しています。今年も100人以上の市民が鐘をついて、戦没者への弔いと、二度と戦争を起こさないという誓いを新たにしていました。オーストリア青年たちもこの行事に参加し、一人ずつ鐘をついて手を合わせていました。大切な人を失う悲しみは、国境を越えて分かち合えるものなのだと実感しました。
国際交流を通じ、様々な文化や感性、価値観に触れることができます。個人でも海外旅行ができる時代になりましたが、多様性が尊重される時代だからこそ、こうした交流事業の重要度は増しているように思います。来年は和歌山からオーストリアへ青年を派遣する予定です。興味のある方は「海友会」ホームページをご覧ください。